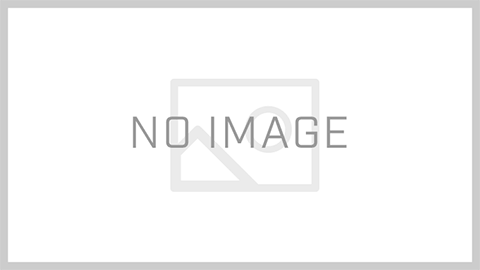初めて曲をミックスするにあたってイコライザー(以下EQ)ってどう使ったらいいかわからんって問題は誰しもが直面する問題だと思います。
当記事はそんな初心者のかたへ簡単なミックスにおけるEQの使い方を書いていきます。
EQを使う前にやるべきこと
これはずばり各トラックの音量調整です。
ミックスにおけるEQの使い道はローカット(無駄な低域のカット)をはじめとしていろいろありますが、そういった手段を使う前に大まかな音量調整はやっておいたほうがよいと個人的に思っています。
各トラックの音量調整は非常に基礎的なことですが奥が深く、ここの土台ができていないとあとからどんどんいろんなプラグインを挿して調整しようとしてわけがわからなくなることが多いです。
ミックスにおいてはプラグインの挿す数が多いと音質劣化も激しくなることが多いので、EQを使用しなくても解決できる問題は予め処理しておいたほうがいいといえます。
音量調整については別途記事にしてありますので、不安があるかたは【ミックスの基礎】音量調整がしっかりと行われているか?の記事を参照していただければと思います。
曲がミックスの工程に入ったらとりあえずはまず全体の音量バランスを整えてみて最低限聞けるような状態にしておくと、各トラックの音量調整では解決できない問題というのがみえてきます。
例えばこの楽器の低音だけいらないなぁーとか、高音だけあげたいなぁーなどです。
EQのブーストについて
当記事ではEQにおけるブーストについては触れません
理由としては特に初心者のうちはカットを中心にミックスをしていってそれぞれの音のバランスをとることを覚えたほうがいいという僕の考え方からきています。
ブーストをするとわかりやすく音を派手にできる反面、全てのトラックを過剰にブーストしすぎて全体の帯域バランスが大きく崩れてしまうということが起こりがちです。
ただブーストをしなければ解決しない場面があることも事実です。
しかしそれについてはカットにある程度慣れてからのほうがうまくいきやすいと思います。
それでは以下は具体的なEQの使い方について解説していきます
1.適度にローカットする

こんな感じでキックやベースなど低域を担当する音が既に配置されている場合、それ以外の音は低域をカットすることが多いです。
理由としてはいろんな音で低域が多く出ていると、ボーカルなどのメインパートをかき消してしまったりするからです。
また、例えばボーカルとかは低域成分にノイズが含まれてることも結構多いので、そういった無駄な音はいらないよねという意味で削ったりもします。
ここから具体例で説明します。
以下、EQ処理をする前としたあとのデモ音源です。
※なるべくいいオーディオ環境で聞いたほうがいいかも
【EQ処理前】
【EQ処理後】
こちらはローカット以外にも複数トラックにEQ処理をした結果となりますので、ローカット以外についてはおって説明します。
ひとまずここで着目してもらいたい点はアシッド音(なんかウニョウニョなってる電子音)です。
この音は一見そんなに低音なんて含んでなさそうなんですが、アナライザーで周波数分布を確認してみると以外と含まれてます

今回のデモ曲ではこの低域の部分はキックとベースが担当してほしいので、このアシッド音に低い部分はいらないなと判断します。
よってアシッド音に対してローカットを適用します。
ここで一点気をつける点はローカットする際のカーブの角度です。
あんまり急激なカーブを選択すると音が細くなるので緩めのカーブでローカットしてます。
EQによってはこのカーブの角度を細かく調整できないものもあるかもですが、できれば調整できるタイプのものを使用したほうがいいと思います。
【EQ処理前】
【アシッド音にローカットのみ適用後】
正直あんまり目立った変化はない感じがしますが、こういう意外と低域が含まれてる音が複数あるとキックやベースの音を邪魔するのでカットしとくのが無難です。
加えて無駄な低域があると他の音を邪魔したり、音圧もあがりにくいなどのデメリットもあります。
ただ、注意事項としてはなにもかも全てローカットしてしまわないことです。
例えばハイハットとかクラッシュシンバルなんかはそもそもローカットを必要としないことがほとんどです。
なぜなら音そのものに低域がそもそも存在しないからです。
よってこういった音色にはローカットが必要ありません。
まずはローカットとは言いましたが今から自分がどんな周波数成分をもつ音色を処理するのかを理解したうえで適度にカットすることが大切です。
ですのでローカットをするときも必要最低限に抑えたほうがいいかなと思います。
ちなみに画像のEQはFabFilterのPro-Q3というEQで画像の通り周波数分布を確認しながら調整できたり、他のトラックの周波数分布と比較して干渉しあってる帯域を視覚的に表示してくれたりする便利機能山盛りプラグインですので、オススメです。
購入はこちら↓

ただそれなりに値段はしますのでセールしているときを狙うか、30日のフリートライヤルを試してみるのがいいかと思います。
もし予算的に厳しいようであれば、無料のMeldaProductionのMEqualizerがオススメです。
細かい音の調整がしやすいのとコンプとかリングモジュレーターとか様々なプラグインがセットでフリーでバンドルされているのでいれて損はないはずです。
周波数分布も表示できるのも大きな利点です。
2.音の灰汁抜きをする
さて、ここで改めてアシッド音だけをローカットした音源を改めてきいてみましょう。
個人的には以下の課題点がみつかりました。
- アシッド音(なんかウニョウニョしてる電子音)の高域が耳に痛い
- シンセのベース音の高域が耳に痛い
- アシッド音とシンセベースの高域がうるさくてハイハットの音が聞こにくい
要するに耳にうるさい高域が多いなと感じました。
よってこういった耳に痛い高域を削っときたいので個別にカットが必要です。
ここでも注意事項なのですが、この作業は前提として、各トラックを全体で鳴らしたときに気になる箇所をカットをするというものです。
例えばアシッド音だけをソロで鳴らしたときには違和感があるけど、オケと混ぜたらあんまり違和感に感じなければカットしなくてもいいです。
今回は僕としては高域うるさいなと感じたのでカットしていきます。


こんな感じです。
ではビフォー・アフターしてみましょう。
【Before】
【After】
高域のほうだけに耳を傾けていただけるとわかりやすいのですが、アシッドとベースの高域の不快な音をカットしたため、耳にやさしい音になりました。
プラスで次の項目である他の音色と同じ周波数を含む音の整理の問題も解決しています。
今回の場合は高域を削ることによって隠れてハイハットが聞こえるようになりました。
いらない音の箇所を探すコツですが一旦Qの幅を広めにとって5dBくらいをマックスに考えてブーストしてみましょう。
その後ブーストの状態を保持したまま右に左に動かしてみましょう。
そうするとやたらキンキンしてたりモワモワしてたりする箇所が見つかったりするのでそこを適度にカットします。
カットする際はブーストしたときのQの幅でやる必要はなく、少し細くしても大丈夫です。
ただし、Qの幅を細くし過ぎると音質劣化も起きやすくなるので、Qの幅には注意しましょう。
この作業をやるだけでも音自体がだいぶすっきりすると思います。
3.他の音色と同じ周波数を含む音の整理
例えばベースがキックと被ってしまって互いに埋もれてしまっている…。
ってなったときにどうするかという話です。
これはお互いの音の周波数成分で被っている箇所があり、そこの棲み分け作業をEQカットで行っていく必要があります。
改めて先程の高域のカットまで終わった音源を聞いてみましょう。
今度は低域に耳を傾けてほしいのですが、なんか低域がですぎな感覚がします。
このデモ曲の場合、曲構成の都合でキックとベースが同時になっている箇所があります。
さらに超低域であるサブベースというものも同時になっているのでキックの低域と役割が被っているとこがあり、互いに邪魔しあっています。
少しわかりにくいのでアシッド音をぬいた音源で確認しましょう。
【ビートのみ】
なんか低域がムワッとしてるといった感じがします。
ここで僕としては超低域であるサブベースはキックより低い帯域を担当してほしかったので、サブベースの超低域をキックからカットし、逆にキックの担当してほしい帯域はサブベースのほうをカットするということにしました。
以下作業結果です。
①キックの周波数カット

②サブベースの周波数カット

そんでもって以下音源のビフォー・アフターです。
【Before】
【After】
低域に耳を傾けてもらえると低いムワッとした部分が解消されキックが少しすっきりしました。
ここらへんは低域のよくでるヘッドホンやスピーカーで比較したほうがいいかもです。
音数が増えてくるほど難しい作業になるのでミックスに慣れてないうちは同時発音数の多い曲構成は避けるのも手です。
アレンジの段階から音の役割を決めてあとの作業をスムーズに行えるようにしておくことが大事かもしれませんね。
初心者の方はとりあえずローカットを頑張ろう
ここまでいろいろ書いてきましたがまずはローカットですね。
これがうまくできてるだけでもだいぶ違います。
低域は聴覚上聞こえにくいためパッと聞いた感じではわからないもんですがアナライザーを通してみると結構入ってたりします。
なのでよくわからん内はアナライザーで周波数分布を確かめて作業に取り掛かりましょう。
ただ慣れてきたらなるべく耳でミックスするようにして、アナライザーは参考程度にしましょう。
EQにアナライザーがついていると便利ですがない場合はフリーでSPANという非常に優秀なスペクトラムアナライザーがあるのでそれを使ってみてもいいかもしれません。